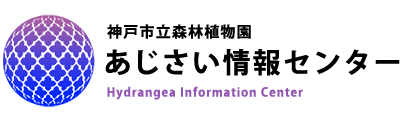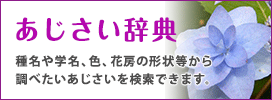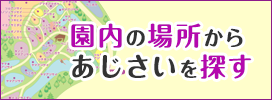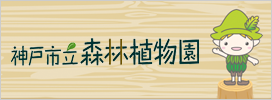あじさいってどんな花?
「あじさい」とは
あじさいは日本では大人から子供まで、誰もが知っている花の一つでしょう。
植物としては単に「あじさい」という植物はなく、多くのアジサイの種類を総称してあじさい(広義)と呼んでいます。
ここでは植物としてのあじさいをカタカナでアジサイと表記します。
アジサイはアジサイ科アジサイ属(Hydrangea ※)に分類される植物です。以前の「新エングラー体系」ではユキノシタ科とされていましたが、近年はDNA解析による遺伝子構造を基にした「APG植物分類体系」が用いられています。
※最近の図鑑などで、アジサイ科の分類が大幅に変更されているものもあります。 今後の変更の可能性はありますが、当園では当面アジサイ属は従来のHydrangeaで表記し、ツルアジサイやタマアジサイ、ノリウツギなどもHydrangeaとしています。
【アジサイの形態と特徴】
- 落葉低木で、枝や茎の中に大きな白い髄がある。暖地性のものは一部常緑もあり。
- 葉は対生に付き、有柄で、通常縁に鋸歯がある。
- 花は、散房花序、まれに円錐花序。
【アジサイの花のつくり】
花は散房花序、まれに円錐花序・中心部に生殖機能のある小さな両性花、縁に萼が変化した装飾花(種子を作らず、中性花ともいう)をつけます。


両性花のアップ
両性花は小さいが花弁、おしべ、めしべなどがあり、稔性があり種子ができる

装飾花のアップ
装飾花は花のように見える部分はガク。
中心に小さな花弁やおしべなどがあるが不稔性
花は変異が多く、両性花、中性花が揃ったものはガク咲き(額縁咲き)、両性花がすべて装飾花になったものはテマリ咲き(玉咲き)などと呼びます。円錐花序のものは穂咲き(ピラミッド咲き)とも呼びます。

ガク咲き(額縁咲き)

テマリ咲き(玉咲き)

穂咲き(ピラミッド咲き)
アジサイの花の色
アジサイの花の色は土壌PHによって変化することはよく知られています。土壌が酸性の場合は青色、アルカリ性の場合は赤色になる、といわれています。
アジサイの花色は「アントシアニン+補助色素+アルミニウム」で青色を発色します。

アントシアニンと補助色素は元々植物の個体が持っているもので、外的な要因はアルミニウムになります。アルミニウムは酸性土壌で溶け出すので、酸性土壌下でアジサイは土壌中のアルミニウムイオンを吸収し、アジサイのアントシアニンと補助色素の作用で青色になり、中性、またはアルカリ土壌では赤色になるといわれています。
日本の山野の土壌は弱酸性の場合が多く、野生下では青色のアジサイが多くみられます。江戸時代に海外に持ち出されたとき、ヨーロッパの土壌はPHが高いため日本で青い種類だったものが赤になったということです。
日本でも、コンクリートの構造物やブロック塀などの際に植栽すると花色が赤系に変化することがあります。
しかし、酸性土壌でも青くならないこともあります。この場合は土壌中にアルミニウムが少ない、アントシアニンや補助色素が少ない、または補助色素の働きを阻害する成分を持っているなどが原因です。他にも、日照や開花後の日数、水分や肥料分の質などによって色素の結合状態は変化すると考えられるので、土壌のPHだけで変化するということでもないようです。
近年の研究により、アルミニウムの濃度は花色と相関関係はなく、リン酸の濃度が高いとアルミニウムと結合し、青色発色を阻害するといことがわかり、アルミニウムではなく、リン酸の濃度が色を決める要素であるとのことが実験で確かめられたそうです。
いずれにせよこのように花色が変化することはアジサイの大きな魅力でもありますが、品種などを判断するにはとてもむつかしい植物ですね。
鉢植えのアジサイ
母の日のころに、園芸店に美しい園芸アジサイがたくさん並び、中でも華やかな赤やピンク系の品種は目を引きます。
鉢植えの場合は鉢の土や肥料の調整が容易なので、自在に花色を調整することができ、同じ品種でも青バージョンとピンクバージョンが売られていたりします。
鉢植えのアジサイを庭などにおろすと翌年花の色が変わることがあります。地植えの場合は土壌の調整などがややむつかしいので、購入した時の花色が変わることがあります。

秋色アジサイ
花が終わると、装飾花の部分の色が変化していきます。緑や、やや赤みを帯びた色に変化していきます。それを特に秋色アジサイといって、品種によっては、観賞の対象にします。
この色の変化は、花が終わって老化し、色素が分解され、葉緑素が見え、次第に褐変する過程で見られます。日照や温度条件などによって発色が異なるようです。
比較的遅めに開花したものや、日陰の涼しいところで開花した花は、うまく夏越しすれば、11月ころまで秋色の花を楽しむことができます。
8月以降のやや乾いた花をタイミングよく採取し、素早く除湿して乾燥状態で保存すると、ドライフラワーとしても楽しめます。

品種により様々な秋色が楽しめる



色々なアジサイのトライフラワーで制作したリース飾り