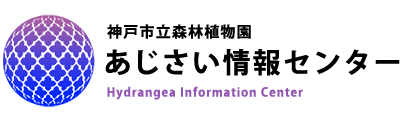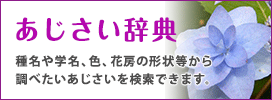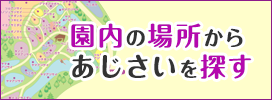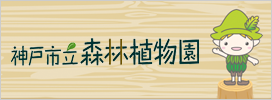神戸と六甲山とあじさい
【神戸市民の花 あじさい】
あじさいは一般の人にもよく知られており、誰でも知っているなじみの深い植物です。
神戸市では、市政80周年と万国博覧会の開催を記念して、広く市民からアンケートを募り、1970年(昭和45年)5月27日に神戸市長をはじめ神戸新聞社の選定委員会で「神戸市民の花」を「あじさい」に決定しました。
神戸の六甲山頂付近には別荘地があり、敷地内やドライブウェイ沿線などに、市民の花になる前からあじさいを植栽していたようです。その頃に植栽されたものは、ヒメアジサイや当時流通していた園芸品種のセイヨウアジサイでした。ハイキングやドライブなどで市民の目を楽しませていたことでしょう。
【六甲山とあじさい】
一方、六甲山地には野生のアジサイの仲間もよく見られます。
5月ごろから咲き出し、美しい白い装飾花をたくさんつけるコガクウツギ、
コガクウツギに続いて、少し青みがかった両性花のみのコアジサイがよく見られます。コアジサイは香りがよく、秋の黄葉も美しい低木です。
この両者は開花期が近く、自然の状態でも交雑種があり、それらをアマギコアジサイと呼んでいます。アマギコアジサイは装飾花を少し持つタイプもあります。

コガクウツギ

コアジサイ

アマギコアジサイ
そして多くの園芸品種のもとになったヤマアジサイも自生しています。
六甲山地のヤマアジサイの自生状況ですが、沢沿いにしばしば見られます。ヤマアジサイは乾燥に弱く、空中湿度が高い環境を好みますので乾いた尾根筋などでは見られません。裏六甲ではスギの人工林の中に群生しているところもあります。スギ林の中は半日陰で湿度が高く、ヤマアジサイの生育環境に適しているようです。
六甲山地では、概ね標高400m以上の所に自生しているようです。群生地では花の変異が多く見られ、ヤマアジサイの宝庫とも言えます。

スギ林の中の自生地


様々な変異がみられる
六甲山の主な構成地質は花崗岩類で風化しやすくもろいのが特徴です。風化してできた真砂土と呼ばれる土で覆われますが、排水が良いのが特徴です。この土は弱酸性で、肥料分も少ないためか、六甲山のヤマアジサイの多くは青色に発色します。
植栽されたアジサイも大きく土壌改良しなければ青色になります。
しかし、建物の基礎や道路の擁壁、縁石付近などでコンクリート構造物に近いところなどでは土壌環境のためか、ピンクに発色しているところも見られます。
しかし、花色の変化は、近年の研究で、土壌酸度によるものではないということがわかってきています。
アジサイの花の色の項目をご参照ください。
【幻のあじさい シチダンカ】
ドイツ生まれの医師であり、博学者のシーボルトは江戸時代に来日し、多くの植物などを採集しヨーロッパに持ち帰りました。
その後『フローラ・ヤポニカ(日本植物誌)』を著し、多くのアジサイの仲間が採録されています。
その中に描かれた八重咲きのヤマアジサイのような植物は、実際に見かけられることがなく長い間『幻のあじさい』とされていました。江戸時代後期の博物学者で、参府旅行中のシーボルトと交流があった、水谷豊文の著書に、シチダンカと書かれている八重咲きのアジサイの図があり、シーボルトのフローラ・ヤポニカのものとよく似ています。
この、シチダンカと思われるヤマアジサイが、1959年に六甲山小学校職員荒木慶治氏によって六甲ケーブル付近で130年ぶりに発見され、室井 綽博士により、シチダンカと同定され、大きな話題を呼びました。
その後、挿し木で増殖され、今では普通に入手できます。元の株は、現在は消失しています。


シーボルトの「フローラ・ヤポニカ」に掲載されているシチダンカの図
神戸市立森林植物園では、当時増殖に努め、市民配布なども行いました。
現在では、シチダンカは普通に園芸店などでも入手でき、ヤマアジサイの有名な品種として普及しています。